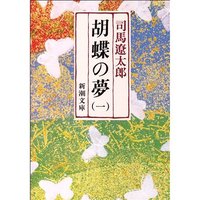2012年01月24日
積ん読解消:吉村昭の「冬の鷹」
昨日の予告通り東京も雪が積もりましたね。
あまり交通機関の乱れもなくよかったですが、やはり都会はこういう物に弱いなと思います。
さて、積ん読を解消できたものをまた御紹介します。
吉村昭さんの「冬の鷹」
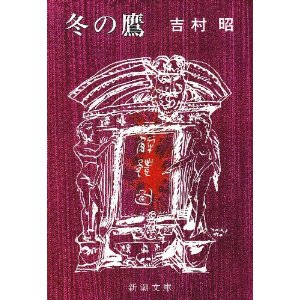
歴史の授業で「解体新書」は必ず出てきますね。
大概杉田玄白の挿絵は落書きされるんですが、みなさんどうでしたか?
本作の主人公は杉田玄白ではなく、前野良沢です。
自分がなぜこの作品を読もうと思ったかに関しては、まずこの漫画を
御紹介しなければいけません。
「風雲児たち」

紆余曲折ありながら現在までなお30年以上続いている作品です。
関ヶ原から始まり、明治維新までを描くとのことで、現在はようやく
桜田門外の変まで来ています。
しかし、非常にボリュームがあって、江戸時代の通史を学ぶのには
うってつけですね。
当時ではあまり取り上げられることがなかった保科正之を前半で取り上げています。
その他にも林子平や高山彦九郎などにもページを割いています。
田沼意次に関しても、従来通りの切り口でなく、進歩的な人物として
描かれています。
→途中で描写が変わったんですが。
その中でひとつの山場は解体新書の翻訳事業。
これを中心として、江戸期の蘭学受容状況、それに啓発された人々を
通して外交史的な色合いが強くなっています。
これから最終的に明治維新につながっていきます。
個人的にはこの作品を通して、興味を持った人物も多いです。
先述した保科正之、高山彦九郎など。
高野長英、大黒屋光太夫など。
このような人物を取り扱った小説を探していくと必然的に行き着くのが吉村昭作品なんですね。
で、色々読んでます、まだまだ読みたいものは色々ありますが、
過去ですと「長英逃亡」「彦九郎山河」などですが。
読んでわかったことは、みなもと太郎さん、タネ本として吉村作品を
活用しているんだなということです。
その中で、「冬の鷹」。
「解体新書」の成立事情に関しては授業でお分かりでしょうから
割愛します。
ただ、その後のこの人々がどうなったかということに関しては
あまり皆さんご存知ないと思います。
自分も「風雲児たち」「冬の鷹」を読むまで知りませんでした。
詳細は是非読んでいただくとして、現実的な杉田玄白と学究の徒としての前野良沢の対照的な生き方。
杉田玄白は名利を手に入れますが、諸事情の元解体新書の訳者に名を連ねなかった前野良沢は困窮していき、家庭的にも恵まれませんでした。
道が別れていきます。
どちらが欠けても成立しなかったとは思いますが、その後はあまりにも対照的でした。
ただ、当時の蘭学の状況というものは現在の常識では図るにはあまりにも重い状況であったようです。
教科書に取り上げられる人々はやはり先進的な人たちですから、この前提を忘れていてはいけませんね。
人の評価は「棺を蓋うて事定まる」という言葉もございます。
みなさんも是非「風雲児たち」と併せて「冬の鷹」をお読みいただければと思います。
江戸時代の見方が変わるはず!
あまり交通機関の乱れもなくよかったですが、やはり都会はこういう物に弱いなと思います。
さて、積ん読を解消できたものをまた御紹介します。
吉村昭さんの「冬の鷹」
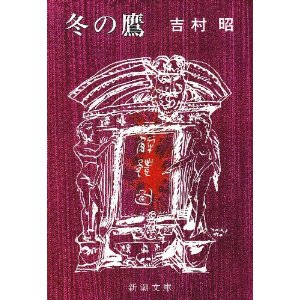
歴史の授業で「解体新書」は必ず出てきますね。
大概杉田玄白の挿絵は落書きされるんですが、みなさんどうでしたか?
本作の主人公は杉田玄白ではなく、前野良沢です。
自分がなぜこの作品を読もうと思ったかに関しては、まずこの漫画を
御紹介しなければいけません。
「風雲児たち」

紆余曲折ありながら現在までなお30年以上続いている作品です。
関ヶ原から始まり、明治維新までを描くとのことで、現在はようやく
桜田門外の変まで来ています。
しかし、非常にボリュームがあって、江戸時代の通史を学ぶのには
うってつけですね。
当時ではあまり取り上げられることがなかった保科正之を前半で取り上げています。
その他にも林子平や高山彦九郎などにもページを割いています。
田沼意次に関しても、従来通りの切り口でなく、進歩的な人物として
描かれています。
→途中で描写が変わったんですが。
その中でひとつの山場は解体新書の翻訳事業。
これを中心として、江戸期の蘭学受容状況、それに啓発された人々を
通して外交史的な色合いが強くなっています。
これから最終的に明治維新につながっていきます。
個人的にはこの作品を通して、興味を持った人物も多いです。
先述した保科正之、高山彦九郎など。
高野長英、大黒屋光太夫など。
このような人物を取り扱った小説を探していくと必然的に行き着くのが吉村昭作品なんですね。
で、色々読んでます、まだまだ読みたいものは色々ありますが、
過去ですと「長英逃亡」「彦九郎山河」などですが。
読んでわかったことは、みなもと太郎さん、タネ本として吉村作品を
活用しているんだなということです。
その中で、「冬の鷹」。
「解体新書」の成立事情に関しては授業でお分かりでしょうから
割愛します。
ただ、その後のこの人々がどうなったかということに関しては
あまり皆さんご存知ないと思います。
自分も「風雲児たち」「冬の鷹」を読むまで知りませんでした。
詳細は是非読んでいただくとして、現実的な杉田玄白と学究の徒としての前野良沢の対照的な生き方。
杉田玄白は名利を手に入れますが、諸事情の元解体新書の訳者に名を連ねなかった前野良沢は困窮していき、家庭的にも恵まれませんでした。
道が別れていきます。
どちらが欠けても成立しなかったとは思いますが、その後はあまりにも対照的でした。
ただ、当時の蘭学の状況というものは現在の常識では図るにはあまりにも重い状況であったようです。
教科書に取り上げられる人々はやはり先進的な人たちですから、この前提を忘れていてはいけませんね。
人の評価は「棺を蓋うて事定まる」という言葉もございます。
みなさんも是非「風雲児たち」と併せて「冬の鷹」をお読みいただければと思います。
江戸時代の見方が変わるはず!
Posted by 情熱小林 at 21:42│Comments(0)
│書評的なもの